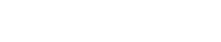2025年10月から公正証書のデジタル化が始まります!
- 時事ニュース
2025年09月24日
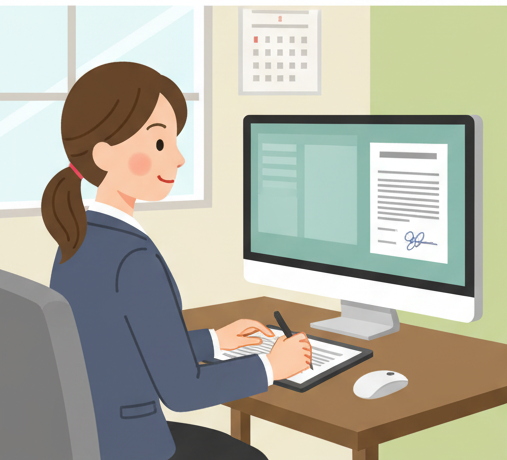
皆さんは「公正証書」と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか?「公証役場に直接行って、実印を押して作成する、少し堅苦しい手続き」という印象が強いかもしれません。しかし、その手続きが2025年10月1日から、デジタル化によって大きく変わります 。
今回は、私たちの生活にも関わりの深い公正証書について、何がどう変わるのか、そのポイントを分かりやすく解説します。
ポイント1:手続きのオンライン化・リモート化
今回の改正で最も大きな変更点は、手続きのデジタル化です。これにより、時間や場所の制約が大幅に緩和されます。
【インターネットでの申請が可能に】
- これまで、公正証書の作成を依頼(嘱託)する際は、公証役場に出向き、印鑑証明書などを提出して本人確認を行う必要がありました 。改正後は、マイナンバーカードなどに搭載されている電子証明書と電子署名を使えば、メールで作成を依頼できるようになります 。これにより、申請のために公証役場へ行く必要がなくなります 。
【ウェブ会議(リモート)での作成が実現】
- 従来は、公証人と対面して公正証書を作成するのが原則でした 。新制度では、嘱託人が希望し、公証人が相当と認める場合に限り、ウェブ会議システムを利用してリモートで公正証書を作成できるようになります 。遠方にお住まいの方や、お仕事の都合で日中に役場へ行くのが難しい方にとって、大きなメリットと言えるでしょう。
【リモート作成の流れ】
- 公証人から送られてくるメールでウェブ会議に参加します 。画面越しに公証人が本人確認と意思の確認を行います 。画面に表示された公正証書の案文を公証人が読み上げ、内容を確認します 。内容に問題がなければ、メールで送られてくるファイルに電子ペンなどで電子サインをします 。公証人も電子署名を行い、公正証書が完成します。
- ※リモートでの作成には、カメラ・マイク付きのパソコンや電子サイン用の機器など、一定の環境が必要です(スマートフォンやタブレットは利用できません) 。
ポイント2:公正証書が「電子データ」に
これまでは紙で作成・保管されていましたが、今後は原則として電子データで作成・保存されることになります 。
- 【署名・押印から「電子サイン」へ】
- 紙の公正証書では署名と押印が必要でしたが 、電子化に伴い、嘱託人はディスプレイなどに手書きする「電子サイン」のみで手続きが完了し、押印は不要になります 。
- 【受け取り方法が選べる】
- 完成した公正証書は、以下の3つの方法からご自身の都合に合わせて受け取ることができます。
- ○電子データを印刷した書面で受け取る
- ○インターネット経由(メール)で電子データとして受け取る
- ○持参したUSBメモリなどにデータを入れてもらう
ポイント3:手数料の改定
デジタル化に伴い、手数料も見直されます 。
- 【負担が軽減されるケースも】
- 特に、ひとり親家庭や高齢者などにとって利用ニーズの高い公正証書については、負担が軽くなるよう配慮されています 。
- 養育費の支払いに関する公正証書:これまで最大10年分の総額を基に手数料が計算されていましたが、今後は最大5年分を基に算定されることになり、手数料が抑えられます 。
- 死後事務委任契約:亡くなった後の手続きを依頼する契約の公正証書手数料が、通常の委任契約の半額になります 。
- 【新たな手数料】
- 公正証書の受け取り方に応じて、新たな手数料が設定されます。
- ○電子データでの交付:1通2,500円
- ○書面での交付:用紙1枚あたり300円
なお、契約金額に応じた基本手数料も、近時の物価上昇などを反映して一部改定されます 。
まとめ
今回のデジタル化は、公正証書をより利用しやすく、身近なものにするための大きな一歩です。特に、リモートでの作成が可能になることで、遺言や任意後見契約、離婚時の養育費の取り決めなど、様々な場面で活用しやすくなることが期待されます。
2025年10月以降、順次指定された公証役場からこの新しい手続きが利用可能になります。とても便利である反面、ご自身だけで対応することに不安を覚えられる方も多いと思います。ご自身のケースでどのように利用できるか、ご不明な点があれば、お近くの公証役場や私達弁護士にぜひご相談ください。